「理解・共感・承認」
2018年、私はこの3つの言葉を外注化の核心として掲げた。そして今、2025年。この原則は変わらない。いや、むしろAI時代だからこそ、より重要になっている。
しかし、ゲームのルールは劇的に変わった。
あなたは今、外注ライターに「AIを使って記事を書いてください」と言えるだろうか? そして、それでも「褒める」ことができるだろうか?
過去の失敗:アドバイス地獄という名の自己満足
2018年の私は、外注ライターに対してダメ出しばかりしていた。
「ここはいいんだけど、もっとここをこうして欲しかった」 「この表現を使っている理由は何ですか?」 「一応私が添削してみましたので記事を見てみてください」
今から考えれば、これは必要とされていないのに小言を言う近所のおせっかいな人そのものである。
ライターからは「ありがとうございます」という返事が来る。しかし、それは気持ちの入っていないお世辞であり、次の仕事につなげるための手段でしかなかった。
結果? 大体2〜3回で終了。そしてまた新しい募集要項をランサーズにコピーペーストする日々。
1記事2000円、3000円払っていた時でさえ、こうだった。
「向こうから求められなければ、ただのおせっかいで不快がられるだけ」——これが、私が外注化に挫折した一回目の教訓である。
転機:褒めるだけで記事の質が劇的に変わった
そこで私は、思い切って戦略を180度転換した。
- 記事に対しての添削や修正の報告 → やめた
- 納品された文章への具体的なアドバイス → やめた
- 誤字脱字の手直し → やめた
代わりに何をしたか?
とにかく褒める。感謝する。共感する。承認する。
以前の私なら「それははっきり言って逆効果です」と言っていただろう。しかし、結果は一目瞭然だった。
わずか数百円の単価にもかかわらず:
- 2日もかけて何千文字もの記事を納品してくれる
- 文字数が少なくても、至るところに「読ませる工夫」がなされる
- 自主的に文章の質がどんどん上がっていく
「外注のWEBライターの中には、お金以外の目的でライティングを行っている人が一定数いる」
この洞察が、すべてを変えた。
2025年の新しい挑戦:AI×外注ライター×あなた
さて、2025年の今。状況はさらに複雑になっている。
なぜなら、外注ライターもAIを使っているからだ。
あなたはこの事実にどう向き合うだろうか?
「AIで書いた記事なんて…」と思うだろうか? 「手抜きだ」と感じるだろうか? それとも、「これは新しいチャンス」と捉えるだろうか?
私は後者を選んだ。
AIを使うライターこそ、積極的に活用すべき理由
ここで重要な認識を共有したい。
AIを使って記事を書くこと ≠ 手抜き
むしろ、2025年において「AIを使わない」方が非効率であり、時代遅れである。
問題は「どう使うか」だ。
レベル1:AIに丸投げするライター
「ChatGPT、この記事を書いて」→ コピペ → 納品
これは論外だ。薄っぺらく、独自性がなく、読者の心を動かさない。
レベル2:AIを補助的に使うライター
リサーチにAIを使う。構成案をAIに出させる。しかし、最終的な文章は自分で書く。
これは悪くない。しかし、まだ効率が悪い。
レベル3:AIと協奏するライター(これが理想)
- 自分の体験や知見を「一言メモ」として残す
- AIにメタ台本を作らせる
- その台本をベースに、自分の言葉で肉付けする
- AIに再度チェックさせ、改善点を洗い出す
このサイクルを回せるライターこそ、2025年の「プロ」である。
あなたがすべきこと:AIリテラシーの教育と、人間的な承認
ここで、あなたの役割が変わる。
やるべきこと1:AIの使い方を「教える」
「AIを使っていいですよ」だけでは不十分だ。
具体的に:
- 「こういうプロンプトで台本を作ってみてください」
- 「AIに直接書かせるのではなく、まず設計図を作らせましょう」
- 「あなたの体験を50文字でメモして、それをAIに分析させてみてください」
このような具体的な指針を示すことで、ライターのAI活用レベルは一気に上がる。
やるべきこと2:褒めるのは「あなた自身」で考える(AIにヒントをもらいつつ)
ここが2025年の微妙なバランスだ。
AIに「この記事を褒めるメッセージを考えて」と頼むことはできる。しかし、それをそのまま使ってはいけない。
なぜか?
人間は、定型文の褒め言葉を見抜くからだ。
2018年、私が受け取っていた「気持ちの入っていないお世辞」——あれと同じことをしてはいけない。
だから、こうする:
- AIに褒めるポイントを分析させる
- 「この記事のどこが良いか、3つ挙げて」とAIに聞く
- しかし、最終的なメッセージはあなた自身の言葉で書く
例えば:
AIが提案した褒めポイント: 「この記事は構成が論理的で、具体例が豊富です」
あなたが書くメッセージ: 「今回の記事、特に3つ目の具体例がすごく刺さりました。あの比喩、読んでて『あー、確かに!』って声出ちゃいましたよ(笑)」
この違いが分かるだろうか?
前者は正しいが、温度がない。 後者は、あなたの感情が入っている。
新しい外注化の形:三者協奏の時代
2025年の外注化は、こうなる:
- ライターはAIを使って効率的にコンテンツを生成
- あなたはAIを使ってライターの成長をサポート
- しかし、人間同士の承認と共感は、決してAIに任せない
この三者協奏こそが、2025年の外注化戦略である。
具体例:AIを活用する外注ライターへのメッセージ術
ダメな例(AI丸投げ)
「いつもご協力ありがとうございます。今回の記事も素晴らしい仕上がりでした。引き続きよろしくお願いいたします。」
→ 温度がない。定型文。誰にでも送れる。
良い例(AI+人間の融合)
「今回の記事、冒頭の『ビフォーアフター』の対比、めちゃくちゃ良かったです! 特に『最先端の自転車レースにママチャリで挑む』っていう例え、読んでて吹き出しそうになりました(笑)。AIを使って構成を作られたんですか? だとしたら、プロンプト設計がかなり上手ですね。この調子でお願いします!」
→ 具体的。感情が入っている。AIの使い方にも言及し、成長を認めている。
AIを使うからこそ、量産が可能になる
2018年、私は月450記事(プロジェクトのみ)を外注で納品していた。タスクを合わせると700を超えた。
2025年の今、AIを活用するライターと組めば、この数字は2倍、3倍になる可能性がある。
しかし、ここで重要なのは:
量だけを追い求めても意味がない
AIで量産されたゴミのような記事を1000本集めても、価値はゼロだ。
重要なのは:
- AIを「設計図」として使う教育
- ライターの独自性と体験を引き出す仕組み
- 人間的な承認と共感による関係性の構築
この3つが揃って初めて、量と質の両立が実現する。
メッセージボードでの会話:AIに頼らない領域
2018年の私は、ライターと1日10〜20往復のメッセージをやり取りしていた。
「時間の無駄」という意見もあるだろう。
しかし、私は今でもこう思う:
ライターさんと話をするのは楽しい
そして、この「楽しさ」こそが、外注化の成功を左右する。
2025年、あなたはAIに「ライターへの返信を考えて」と頼むかもしれない。それ自体は悪くない。時間の節約にもなる。
しかし、最終的なメッセージは必ず自分で見直し、自分の言葉を加えること。
なぜなら、ライターはあなたという人間と仕事をしているのであって、AIと仕事をしているのではないから。
失敗から学んだ逆説:全部カットしたらうまくいった
2018年、私は「これだけは絶対に必要だ」と思っていたものをすべてカットした:
- 添削
- アドバイス
- 修正指示
そして、うまくいった。
2025年、私は新しいものを追加した:
- AIリテラシーの教育
- プロンプト設計のサポート
- メタ台本の概念の共有
しかし、カットしたものは今でもカットしたままだ。
なぜなら、ライターが自主的に成長する環境こそが、最も効率的だからだ。
あなたが明日からできること
ステップ1:ライターにAI活用を推奨する
「AIを使ってもいいですよ」ではなく、「AIをこう使ってください」と具体的に示す。
例: 「記事を書く前に、まず50文字程度の『一言メモ』を作ってください。そのメモをChatGPTに投げて、『この一言から、5W1H分析、感情の流れ、ターゲット像を含むメタ台本を作ってください』と指示してみてください」
ステップ2:褒めるポイントをAIに分析させる
納品された記事をAIに読み込ませ、「この記事の良い点を3つ挙げて」と聞く。
しかし、そのまま使わない。あなた自身の言葉で再構成する。
ステップ3:定期的に「AI活用のコツ」を共有する
「最近、こういうプロンプトを試したらすごく良かったですよ」 「このAIツール、使ってみました?」
こういう情報共有が、ライターの成長を加速させる。
ステップ4:人間同士の会話は、決してAIに任せない
世間話、冗談、励まし——これらはあなた自身の言葉で。
ここだけは、2018年と変わらない。
結論:AI時代の外注化は「教育」と「承認」の両輪
2018年、私は「褒める・感謝・共感・承認」を外注化の核心とした。
2025年、私はこれに「AI活用の教育」を加える。
しかし、本質は変わらない。
ライターの方から「この人のためなら全力で書く」と思っていただく
これがすべてである。
AIは道具だ。しかし、道具の使い方を教えるのは人間であり、道具を使って生み出された成果を承認するのも人間である。
2025年、外注化の成功は「AI×人間」のバランスにかかっている。
- AIに任せるべきこと:効率化、分析、アイデア出し
- 人間がやるべきこと:教育、承認、共感、関係性の構築
この境界線を見極めたあなたは、月1000記事どころか、月2000記事、3000記事さえ視野に入る。
しかし、忘れないでほしい。
量ではなく、質と関係性
これが、時代を超えて変わらない真理である。
2025年版追記:
「仕事関係のメッセージで涙が出てしまったのはこれが初めてです」
2018年、あるライターからこんなメッセージをもらった。
AIがどれだけ進化しても、この感動は人間にしか生み出せない。
そして、この感動こそが、外注化を成功させる最大の秘訣なのである。
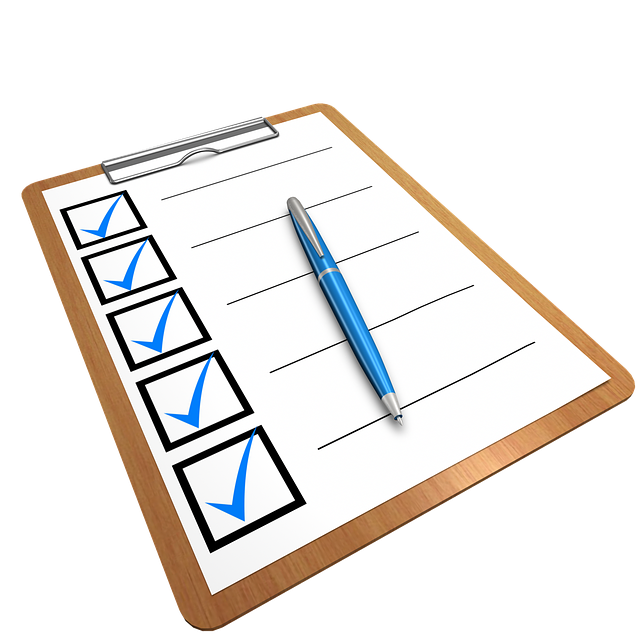
コメント